相続登記
目次
相続登記とは
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった被相続人(亡くなった方)から相続人に変更するための手続きです。不動産の権利関係は法務局において登記されているので、法務局に申請して登記手続きを行います。
相続登記の時期
相続登記はいつまでに行わなければならないという制限はありませんが、時間が経過すると法定相続人の1人が亡くなり、その子供達が相続人になるなど、印鑑をもらわなければならない関係者増えていき手続きが煩雑になることがあります。相続登記はお早めがおすすめです。
相続登記の種類
相続登記には3つの場合があります。
- 法定相続分の通りに登記する場合
- 遺産分割協議に基づいて登記をする場合
- 遺言に基づいて登記をする場合
A 法定相続分の通りに登記をする場合
被相続人が亡くった瞬間に、法律上は法定相続人が法定相続分に従って不動産を共有している状態になります。もちろん、相続登記をするまでの間は、遺産に属する不動産の名義は被相続人のままです。しかし、死者が所有しているという状態は法律上はあり得ません。つまり、本当は法定相続人の共有になっているのに、登記だけは旧所有者である被相続人の名義のままとなっており、登記が実際の権利関係を正しく反映していない状態、すなわち真実と登記にずれが生じている状態になるのです。
そこで遺産分割協議が完了していなくても、相続登記の申請することで、まずは法定相続分のとおりの共有名義とすることができるのです。これが「法定相続の通りに登記をする場合」です。この登記の申請は法定相続人の1人が単独で行うこともできます。
被相続人の死亡
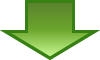
法定相続人の共有
この共有状態を遺産共有といいます。遺産共有は遺産分割により誰がどの財産を確定的に取得するのかを定めるまでの暫定的な共有です。
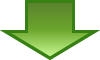
遺産分割
最終的な取得財産が確定します。
B 遺産分割協議に基づいて登記をする場合
遺産分割協議が成立すると、どの相続人がどの財産を取得するのかが確定的に決まり、この結果に基づいて相続登記を行います。これが「遺産分割協議に基づいて登記をする場合」です。Aの登記をせずにいきなりBの登記ができるため、通常は遺産分割が終了するまでは相続登記をせず被相続人の名義のままとしておいて、遺産分割協議が成立したところでBの登記をすることになります。
C 遺言に基づいて登記をする場合
A、Bの登記は不動産を取得する者について遺言書がない場合です。遺言書がある場合には、遺言書の内容に従って相続登記をすることになります。
相続登記を弁護士に依頼するメリット
相続登記を行うことができるのは弁護士と司法書士だけです。相続登記は司法書士が行う場合が多いですが、弁護士は登記だけでなく相続人間の紛争に関するあらゆる問題を取り扱うことができるので、全体的な処理を任せる場合には弁護士への依頼がお勧めです。
たとえば当事務所に相続登記をご依頼の場合、登記手続きの準備段階で、協力を拒む相続人がいた場合は、その相続人との交渉も当事務所にご依頼いただくことができます。
相続登記の弁護士費用
弁護士費用のページをご覧下さい。






